図書館で静かにする理由について、私も何度か「なんでそこまで静かにしないとダメなの?」って思ったことがあるんです。
でも、その理由を知ると「なるほど、そういうことか」って納得できたんですよ。
まず最初に要点だけをまとめると……
- 図書館の静寂は、すべての利用者が集中できる環境を守るため
- 音のない共有空間として設計されており、小さな音でも響きやすい
- 子ども連れでも基本ルールは同じだが、児童コーナーは緩和されることも
- 黙認される音は生活上不可避な音のみで、言語音は避けるべき
この記事では、図書館で静かにしなきゃいけない理由を文化的な視点も交えて解説していきます。
それでは、具体的に見ていきましょう。
図書館で静かにする理由とは?

図書館で静かにする理由は、単なるマナーの問題だけじゃないんです。
実は、図書館という公共空間の設計思想や、人間の集中力に関する科学的な理由が背景にあります。
ここでは主に以下の4つのポイントから解説していきますね。
- 誰もが安心して集中できる空間を守るという公共施設としての役割
- 音のない共有空間として建物自体が設計されている構造的理由
- 静かな環境下では小さな音でも響きやすいという音響特性
- 職員が注意を行うタイミングと、その背景にある公平性の考え方
それぞれ詳しく見ていきましょう。
一番の理由は「誰もが安心して集中できる空間を守るため」
図書館で静かにする一番の理由、それはすべての利用者が資料の閲覧、調査、学習といった本来の目的を達成できるよう、集中できる環境を確保・維持することなんです。
つまり、静寂は単なるマナーじゃなくて、学習や調査研究の「質」を保証するための環境条件として重要視されているわけですね。
集中力の維持には静寂が不可欠
認知心理学的な観点から見ると、会話や予測不能な物音などの「言語音」は、人間の集中を最も妨げやすいとされています。
私も経験があるんですが、静かに勉強していると、隣の人のひそひそ話が妙に気になって、まったく集中できなくなることってありますよね。
静かな環境は、利用者が外部の干渉を受けずに思考し、深く集中するために不可欠なんです。
公平性の確保という視点
図書館は公共の施設として、すべての人に平等に学習の機会を提供する場所なんですよ。
だから、音による不利益を被る人が出ないよう、共通の静寂ルールが設けられているわけです。
「私は音があっても集中できるから」という個人の感覚だけで判断すると、音に敏感な人が困ってしまうわけですね。
心理的な安心感を与える空間
「静かである」という空間の特性は、利用者に「ここでは集中して良い」という心理的な安心感を与えます。
自宅だと家族の声やテレビの音、カフェだとBGMや周りの会話が気になりますが、図書館なら「みんな静かにしている」という安心感があるんですよね。

図書館は”音のない共有空間”としてつくられている
図書館の建物の設計や運営ルールは、音を最小限に抑えることを前提につくられているんです。
これは単なる後付けのルールじゃなくて、建物そのものの設計思想なんですよ。
音の吸収と反響の特性
多くの図書館では、カーペットや吸音材が使用されています。
ただ、広い空間は音が反響しやすく、特に静かな場所では小さな音が遠くまで伝わりやすいという特性があるんです。
私もM区図書館で勉強していたとき、3列向こうの人のキーボード音がカタカタと聞こえてきて、「こんなに響くんだ」って驚いたことがあります。
高いレベルの静寂を提供する公共サービス
図書館は、自宅やカフェ、学校といった他の場所では得られにくい、高いレベルの静寂を公共サービスとして提供する役割を担っているんですよね。
これって意外と見落とされがちなんですが、静かな環境を無料で提供してくれる場所って、実はそんなに多くないんです。
- 自宅:家族の生活音、テレビ、来客などがある
- カフェ:BGM、他の客の会話、注文の呼び出し音がある
- 学校:授業の移動時間、部活動の音、友人との会話がある
- 図書館:音を最小限に抑えた環境が保証されている
だからこそ、図書館は「静かに集中したい人」にとって貴重な場所なんですよ。

小さな声でも意外と響くから注意が必要
図書館の静かな環境下では、私たちが日常で気にも留めないような小さな音でも、他の利用者にとっては大きな騒音として感じられることがあるんです。
これ、実際に体験してみないとなかなか実感できないんですよね。
音のコントラストが意識を奪う
周囲の音が静かであればあるほど、わずかな音(コントラスト)が際立ち、意識を奪いやすくなります。
例えば、騒がしい駅のホームでは誰かの咳払いなんて気にならないですが、図書館で同じ咳払いをすると、周りの人がビクッとすることってありますよね。
これは音の大きさそのものじゃなくて、周囲の静けさとのコントラストが問題なんです。
具体的に響く音の例
以下のような音は、静かな図書館では意外と響きます。
| 音の種類 | 響き方 | 注意点 |
|---|---|---|
| ひそひそ話 |
小声でも隣や前後の席には 内容が聞き取れるレベル |
話す場合は館外か 指定されたスペースで |
| キーボードの打鍵音 |
リズミカルな音が 集中を乱す |
静音キーボードの使用や 打ち方を柔らかく |
| ビニール袋や包装紙の音 |
ガサガサという音が 広範囲に響く |
飲食物の出し入れは最小限に |
| 咳や鼻をすする音 | 突然の音が周囲を驚かせる |
やむを得ない場合は手で押さえる 連続する場合は席を離れる |
これらの音は、一人の利用者にとっては些細なものであっても、集中している他の多くの人々の「集中を中断させる引き金」となってしまうんですよ。
私自身、ある図書館でティッシュの袋を開けたとき、思った以上に音が響いて恥ずかしい思いをした経験があります。

職員が注意するタイミングと理由
図書館職員が利用者に静粛に関する注意(声かけ)を行うのは、主に静寂ルールが破られ、他の利用者に迷惑が及んでいると判断した時なんです。
つまり、職員による注意は、特定の個人を咎めるためではなく、図書館という公共の場における公平な利用環境を維持し、すべての利用者の権利を守るために行われます。
注意されるケースと理由
以下の表に、職員が注意するタイミングと主な理由をまとめました。
| 注意するタイミング | 主な理由 |
|---|---|
| 私語・談笑 |
静粛を最も乱し 他の利用者の集中力を奪うため |
| 携帯電話の着信・通話 |
予期せぬ大きな音や会話が 利用環境を破壊するため |
| 居眠り時のいびき |
席の長時間占有と 睡眠音による迷惑のため |
| 継続的な物音 |
頻繁な咳、物を床に落とす ガサガサと音を立て続けるなど 静寂を乱す行為が続く場合 |
| 飲食 | 咀嚼(そしゃく)音や包装紙の音が迷惑。 資料汚損のリスクを防ぐため |
私も学生時代、友達と図書館で勉強していて、つい話し込んでしまったことがあるんです。
そしたら職員の方が来て、「申し訳ないのですが、他の方の迷惑になりますので……」と丁寧に注意されました。
そのとき、「あ、自分たちだけの問題じゃないんだな」って気づいたんですよね。
注意される前に自分で気づくことが大切
職員に注意されるということは、すでに他の利用者に迷惑をかけている状態なわけです。
だから、注意される前に自分で気づいて、音を抑える配慮ができるといいですよね。
- 周囲を見回して、自分の行動が目立っていないか確認する
- 他の人が振り返ったり、こちらを見たりしていないか注意する
- 自分が出している音を客観的に想像してみる
- 疑問があれば、カウンターで職員に確認する
なにはともあれ、職員の注意は個人攻撃じゃなくて、みんなが快適に使えるための声かけなんだと理解しておくことが大切です。

図書館で静かにする理由に関するQ&A
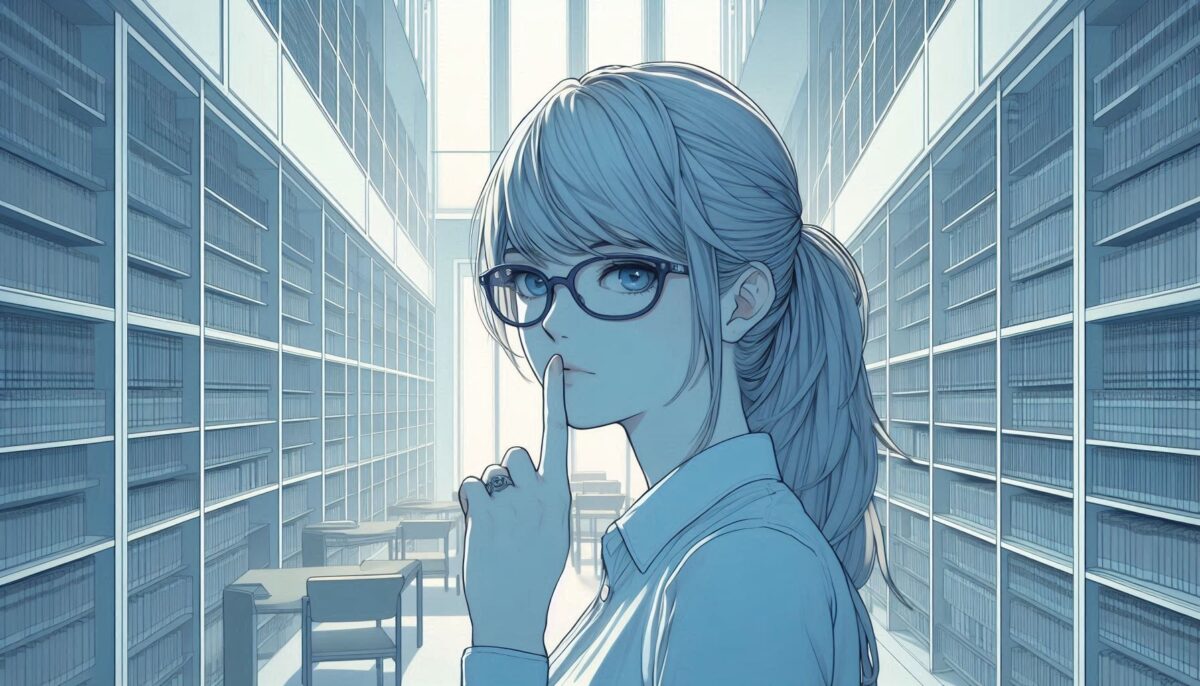
図書館の静寂ルールについて、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。
特に気になるのが以下の2点ですよね。
- 子ども連れの時も静かにしないといけないのか
- どの程度の音なら黙認されるのか
それぞれ詳しく見ていきましょう。
子ども連れの時も静かにしないといけない?
原則として、静かにする配慮は必要ですが、「児童コーナー」など特定のエリアでは、ルールが緩和されていることが多くあるんです。
ただ、これはエリアによって対応が変わるので、注意が必要なんですよ。
一般エリア(閲覧室・書架)の場合:厳格な静寂が必要
児童書以外の一般書架や、学習を目的とした閲覧席では、子どもであっても大人と同様に静粛な利用が求められます。
これは「子どもだから仕方ない」という理屈が通らないエリアなんですよね。
具体的には、以下のような行為は禁止されています。
- 大声や走り回る行為:多くの図書館で、「走る」「大声を出す」行為は、他の利用者の迷惑となるため、保護者が注意するよう明記されています
- 泣き止まない時の対応:赤ちゃんや幼児が泣き止まない場合は、一旦図書館の外に出て、落ち着くまで待ってから再入館するよう求める図書館もあります
小さな子が泣き出して、親御さんが慌てて外に連れ出す場面を何度か見たことがあります。
あれは親御さんも大変だと思うんですが、やっぱり周りへの配慮として必要なことなんですよね。
児童コーナー(絵本・読み聞かせスペース)の場合:緩和されることが多い
多くの図書館では、子どもの読書活動の特性を考慮し、児童書コーナー(親子エリア)を一般エリアとは「音」のルールを分けて運用しています。
これは子どもの学習スタイルに合わせた配慮なんですよ。
具体的には、以下のような対応がされています。
| 対応内容 | 詳細 |
|---|---|
| 「おしゃべりOK」の表示 |
児童コーナーでは 「お話ししながら絵本を楽しんでいただけます」 といった表示を掲示。 絵本を読み聞かせたりする程度の音を許容 |
| 親子の声の重要性 |
子どもが本に出会う大切な時間として、 親子が内容について「ひそひそ声」で話し合ったり 短い単語やジェスチャーで意思疎通したりすることは、 マナーの範囲内 |
| ゾーニング(区域分け) |
「静かに過ごしたい人」と 「子どもと利用したい人」のニーズを分離。 |
とはいえ、児童コーナーでも大声で騒いだり、走り回ったりするのはNGです。
あくまで「小声での会話や読み聞かせ」が許容されているだけなんですよね。
親が子どもに伝えるべきこと
図書館は誰もが利用する公共の場であり、静かな環境を保つことが求められます。
親は子どもが騒いだり走り回ったりしないように注意し、静かに過ごすよう導く必要があるんです。
- 「図書館は静かにする場所」という基本ルールを伝える
- 「周囲の人への配慮」をわかりやすく説明する
- もし子どもがぐずったり泣いたりした場合は、周囲の迷惑にならないようすぐに外へ出る
- 児童コーナーでも「小さな声で話す」ことを教える
私の友人も子どもを図書館に連れて行くときは、事前に「図書館では静かにしようね」って約束してから行くそうです。
そういう準備が大切なんだなぁ、と。

黙認される「音」の種類や程度は?
「黙認される」という表現は公式ルールに存在しませんが、図書館が目指す静寂レベル(40dB台が目安とされます)から逸脱しない、生活上不可避な音や、学習に付随する一部の音は、許容範囲として見なされていると考えられます。
つまり、完全な無音を求めているわけじゃないんですよね。
許容範囲とされる音(生活上・学習上不可避な音)
静粛な環境下で、他の利用者の集中を著しく妨げないと見なされる音は以下の通りです。
| 音の種類 | 許容範囲の目安 | 留意点 |
|---|---|---|
| 紙をめくる音 |
資料やノートの ページをめくる音 |
乱暴にめくったり 大きな音を立てて資料を扱うのは避ける |
| 筆記音 |
ノートにペンを走らせる音 鉛筆の音 |
ペンや鉛筆の音も静かな環境では響くため 筆圧や動きに配慮が必要 |
| 軽い咳・くしゃみ | 生理現象による一時的な音 |
意図的に咳払いしたり 連続して続く場合は 席を離れるなどの配慮が必要 |
| 私的な足音 |
席への移動や書架での 資料探しの際の足音 |
走り回る ヒールで大きな音を立てるなど 不必要な大きな音を出すのは マナー違反 |
これらの音は、図書館を利用する上で避けられない音なので、ある程度は許容されています。
ただし、「許容されている」からといって、配慮しなくていいわけじゃないんですよ。
許容されない音(抑制すべき音)
音の大きさに関わらず、特に許容されないのは、「言語音」や「予測不能な不快音」です。
以下のような音は、静かな図書館では避けるべき音とされています。
- 言語音:私語、ひそひそ話、電話の着信音や通話、独り言
- 不快音:菓子や食品の包装を開けるガサガサという音、スマホの操作音やシャッター音、キーボードの強い打鍵音、居眠りのいびき
私も以前、図書館で電話が鳴ってしまって、慌てて外に出たことがあります。
マナーモードにし忘れていたんですが、あの時の周りの視線は今でも忘れられないですね。
40dBという基準
図書館の静寂とは、「一切の音がない状態」ではなく、「他の利用者が学習や読書に集中することを妨げないレベルの音量」を意味します。
利用者は、自分が発する音が40dB(静かな住宅地や図書館の平均的な騒音レベル)を超えないよう、常に意識的に配慮する必要があるんです。
ちなみに、40dBってどのくらいかというと……
- 静かな住宅地の昼間
- 図書館の閲覧室
- 深夜の郊外
こんな感じの静けさなんですよ。
つまるところ、図書館では「生活音」は許容されるけど、「意図的な音」や「避けられる音」は控えるべきということですね。

図書館で静かにする理由のまとめ
さて、ここまで図書館で静かにする理由について詳しく見てきました。
最後に、この記事の内容をおさらいしておきましょう。
- 図書館の静寂は、すべての利用者が集中できる環境を守るための環境条件
- 図書館は音のない共有空間として設計されており、小さな音でも響きやすい構造
- 子ども連れでも基本的に静かにする配慮が必要
- 児童コーナーではルールが緩和されることも
- 黙認される音は生活上不可避な音のみで、言語音や不快音は避けるべき
- 職員の注意は個人を咎めるためではなく、公平な利用環境を守るため
図書館で静かにする理由は、単なるマナーの問題じゃなくて、公共の場としての役割や、集中力を維持するための科学的な根拠があるんですよね。
「なんで静かにしないとダメなの?」という疑問が、少しでも解消されたなら嬉しいです。
図書館は、静寂という貴重なサービスを提供してくれる場所なので、みんなでその環境を守っていきたいものですね。

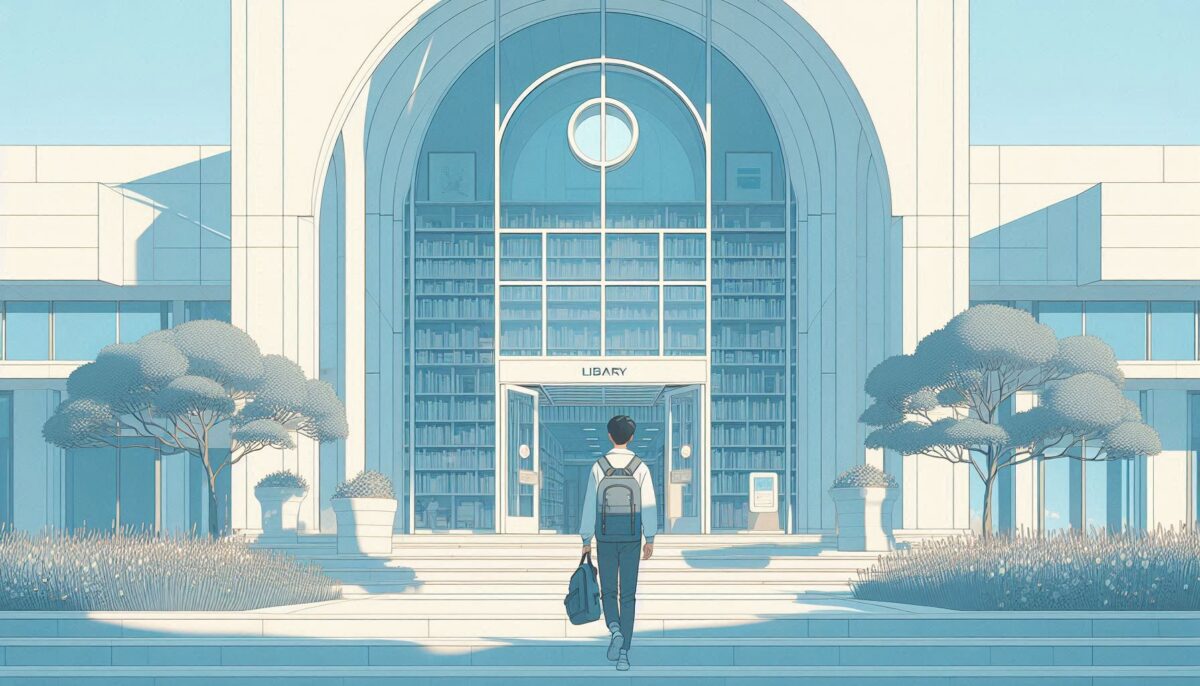
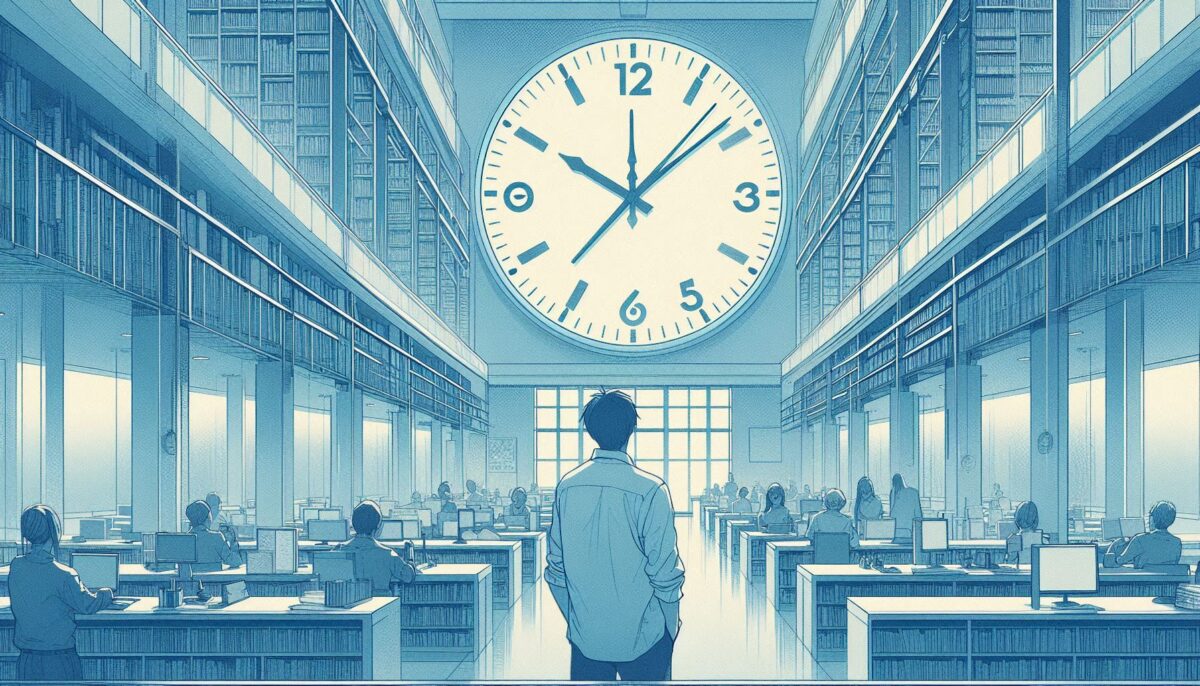
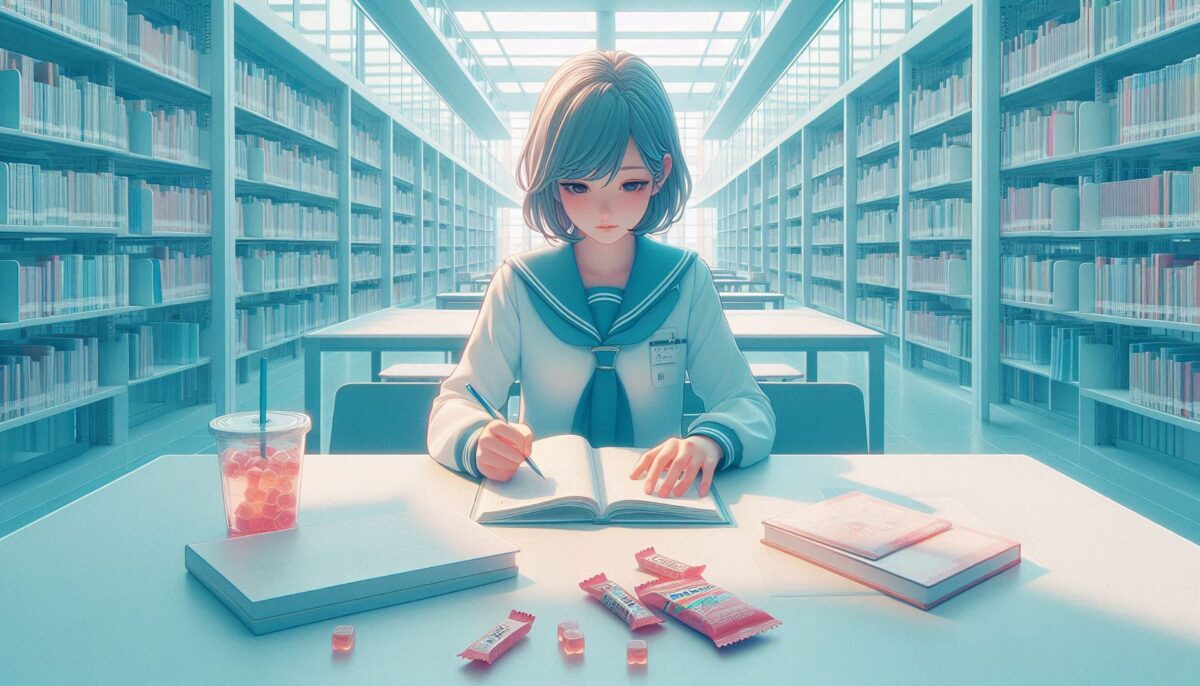
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://library-navi.com/why-you-should-be-quiet-in-the-library/trackback/