図書館は市外の人でも勉強できるのか、気になりますよね。
私も学生時代から図書館にずっと通ってきて、引っ越しや転勤で色々な地域の図書館を利用してきたんですが、基本的には市外の人でも入館して勉強することは自由なんです。
ただ、図書館によってはローカルルールがあったり、自習室の利用に制限があったりすることもあるんですよね。
まず最初に要点だけをまとめると……
- 公共図書館は市外の人でも入館・閲覧・自習は基本的に自由
- 自習室の利用については各館の方針によって制限がある場合も
- 県立図書館や大学図書館も勉強目的で使いやすい選択肢
- 資料の貸出は居住地や在勤・在学地が条件になることが多い
この記事では、図書館を利用する際のルールや、市外の人が使いやすい図書館の種類、よくある疑問について詳しく解説していきますよ。
それでは、具体的な利用方法を見ていきましょう。
図書館は市外の人でも勉強できる?

結論から言うと、日本の公共図書館は市外の人でも利用できるんです。
なんていうか、図書館って地域住民のためだけの施設というイメージがあるかもしれませんが、実際には図書館法に基づいて、居住地に関わらずすべての人にサービスを提供することが求められているんですよね。
以下のポイントを順番に解説していきます。
- 入館と資料閲覧、自習は原則として誰でも可能
- 自習室の利用ルールは図書館ごとに異なる
- 県立図書館や大学図書館という選択肢もある
誰でも入館可だし勉強するのも自由
公共図書館(市区町村立図書館)は、その設置目的から、市外や県外の人であっても、原則として入館して資料の閲覧や館内での勉強(自習)をすることは自由です。
図書館法に基づく図書館の原則として、居住地、年齢、国籍などに関わらず、すべての人にサービスを提供することが求められているんです。
館内で資料を閲覧したり、持ち込んだ資料で机に向かって勉強したりする行為は、図書館の基本的な機能に沿ったものなんですよね。

とはいえ、サービスによっては利用者の居住地や在勤・在学地を要件としているものがあります。
制限される主なサービスには以下のようなものがあります。
- 資料の館外貸出:ほとんどの公共図書館では、その市町村の在住・在勤・在学であることや、隣接する自治体の住民であることを条件としている
- インターネット予約:貸出同様、利用者登録が必要なサービスは居住地等が条件となる
- 自習室の優先利用:混雑時に市民を優先するルールを設けている図書館もある
つまり、館内で本を読んだり自分の教材で勉強したりするのは自由だけど、本を借りて帰るのは居住地が関係してくるということ。
自習室の利用は各館の方針によって異なる
図書館の中には、学習目的の利用者を対象とした「自習室」を設けている場合があるんですが、その利用ルールは各図書館の方針によって異なります。
自習室の利用パターンは大きく分けて2つあるんですよね。
原則自由な場合
自習室であっても、特別な条件を設けず、すべての来館者に利用を許可している図書館もあります。
こういった図書館では、市外の人でも気兼ねなく自習室を使えるんです。
ただし、混雑時には座席の利用時間を制限したり、長時間の席取りを禁止したりするルールがある場合も。
市外利用者を制限する場合
一部の図書館では、混雑緩和や市民サービスの優先を目的として、自習室の利用を当該市町村の在住・在勤・在学の利用者に限定している事例もあります。
具体的には以下のような制限があることも。
- 座席を利用する際に利用者カードの提示を求められる
- 繁忙期(試験シーズンなど)は市民優先となる
- 自習室の事前予約が市民のみ可能

やっぱり、市民の税金で運営されている施設なので、市民を優先するという考え方は理解できるところ。
でも、完全に利用できないわけではなく、空いている時間帯なら使えることも多いんですよ。
勉強目的で使いやすい「県立図書館」・「大学図書館」もある
公共図書館以外にも、勉強場所として適した施設があって、市外の人でも利用しやすい場合があるんです。
県立図書館(都道府県立図書館)
県立図書館は、市町村立図書館を支援する役割を担うとともに、高度な調査研究機能を持つことが特徴なんですよね。
県立図書館は県民全般の利用を想定しており、県内であれば市町村を問わず、資料の貸出や館内利用が可能です。
県立図書館の特徴としては以下のようなものがあります。
- 広い閲覧席が設けられていることが多い
- 研究個室(利用制限あり)を備えている場合もある
- 静かに集中して勉強しやすい環境が整っている
- 専門的な資料が豊富に揃っている
つまるところ、市町村立図書館よりも広域の利用者を対象にしているので、市外の人にとっては使いやすい選択肢なんです。
大学図書館(私立・公立)
大学図書館も、地域住民への開放を進めているところが多くて、市外の人でも利用できる可能性があるんですよ。
利用対象は大学によって大きく異なります。
| 利用タイプ | 条件 | 主なサービス |
|---|---|---|
| 無料開放 | 身分証明書の提示のみ 居住地不問 |
閲覧席の利用(自習)可 貸出は有料会員登録が必要 |
| 地域制限型 | 近隣の特定市町村に在住・在勤・在学 | 施設利用可 貸出条件は個別に異なる |
| 会員制 | 年会費の支払い | 閲覧・貸出ともに可 |

ラーニングコモンズ(※注:大学図書館などに設けられる学生が主体的に学習するための「場」のこと)といった最新の学習施設を備えている大学も増えているんです。
ただ、大学図書館は利用条件が個々に大きく異なるため、利用したい大学の「図書館利用案内(学外の方へ)」のページで、一般利用者の利用資格を必ず確認してください。
図書館は市外の人でも勉強できる?に関するQ&A

市外の人が図書館を利用する際によくある疑問について、詳しく解説していきます。
なにはともあれ、実際に利用する前に知っておきたいポイントを2つ紹介しますね。
- 各図書館のローカルルールの有無
- 貸出サービスの利用条件
場所によってローカルルールはある?
はい、図書館には設置主体や種類によってローカルルール(個別の利用制限)が存在していて、特に自習室や学習席の利用に関して、市外の利用者に対して制限を設けている場合があります。
公共図書館(市区町村立)のルール
ほとんどの市区町村立図書館は、入館と資料の閲覧・自習は誰でも自由に認めているんですが、一部の設備やサービスは優先度をつけるためにローカルルールがあるんです。
具体的な制限の例を見ていきましょう。
- 自習室の制限:閲覧席全体ではなく、特に「自習室」や「学習席」を設けている場合、当該市町村の住民を優先するために、利用を住民・在勤・在学者に限定している事例がある
- 混雑時の優先順位:席の混雑緩和と、市民へのサービス優先を目的としている
- 例外的な制限:極めて稀だが、極端に混雑する地域の図書館では、災害時や繁忙期に限り、座席の利用を住民のみに限定するなどの一時的な制限を設けることもある
実際の事例を挙げると、Y市立図書館では市内在住・在勤・在学者が主な利用対象で、市外利用者は相互利用協定がある場合を除き、館外貸出の利用者番号付与が難しいケースがあります。
また、I市立図書館では混雑時は市内在住者優先で閲覧席利用制限や貸出制限があるんですよね。
C市立図書館も市内在住・在勤・在学者が原則利用者対象で、市外の制限事項を設けています。

大学図書館のルール
大学図書館は、そのローカルルールが最も多様なんです。
大学は本来、学生・教職員のための施設であるため、一般の地域住民への開放は大学の方針によって大きく異なります。
- 厳格な制限:卒業生や特定の地域住民(近隣の市区町村)のみに利用を限定しているケース
- 比較的開放的:身分証明書があれば、居住地を問わず館内での閲覧・自習のみを許可しているケース
- 完全会員制:年会費を支払うことで、誰でも利用できるシステムを採用しているケース
したがって、自習目的で長時間滞在したい場合は、事前に利用したい図書館の公式ウェブサイトの「利用案内」で、座席利用の条件を確認することが重要です。
貸出は市民じゃないと無理?
原則として、資料の館外貸出は、その図書館がサービスを提供する範囲の住民ではないと無理な場合がほとんどです。
貸出サービスの利用には、利用者カード(貸出券)の発行が必要であり、このカード発行には、多くの図書館で条件を設けているんですよね。
公共図書館の場合
貸出の条件は、その図書館の維持・運営費を負担している住民の利益を優先するために設けられているんです。
最も一般的な要件は以下の通り。
- 当該市区町村に居住している人
- 当該市区町村に在勤している人
- 当該市区町村に在学している人
さらに、広域利用の特例として、隣接する特定の市区町村の住民に対しても、相互協力協定に基づき貸出を認めている場合があります。
みたいな感じで、市外の人であっても、隣接自治体の住民であったり、勤務先・通学先がその市内にあったりする場合は貸出が可能なんですが、それ以外の遠隔地の市外住民は、原則として貸出はできません。
例えばK市立図書館では市内の居住・勤務・通学の証明が必要で、一般的には市民以外の貸出利用は難しいんです。
県立図書館の場合
県立図書館は県民全般へのサービスを目的としているため、県内在住・在勤・在学であれば、市町村を問わず貸出が可能です。
これは市町村立図書館よりも広い範囲をカバーしているということ。
大学図書館の場合
大学図書館での貸出は、一般開放されていないか、または有料の会員制度を利用する必要があることが一般的なんですよね。
- 会員制度:一般利用者は、年会費を支払って「賛助会員」などになることで、資料の貸出サービスが受けられる場合がある
- 卒業生優遇:その大学の卒業生に限り、無料または格安の年会費で貸出を許可している事例も多い

結局のところ、利用ルールや貸出冊数や期間は図書館により異なっていて、相互貸借や他都市との連携で借りる方法がある場合もあるので、事前の確認が大切なんです。
図書館は市外の人でも勉強できるのまとめ
図書館は市外の人でも勉強できるかどうかについて、詳しく解説してきました。
最後に、この記事の要点を振り返っておきましょう。
- 公共図書館は市外の人でも入館・閲覧・自習は基本的に自由
- 自習室の利用は各図書館の方針によって異なり、市民優先の場合もある
- 県立図書館は県内であれば市町村を問わず利用できる
- 大学図書館も地域住民に開放している場合がある
- 資料の館外貸出は居住地や在勤・在学地が条件になることが多い
- 各図書館のローカルルールがあるので事前確認が重要
市外の人でも図書館での閲覧や勉強は可能ですが、貸出など一部のサービスには居住地域の制限があります。
利用予定の図書館の公式情報を事前に確認して、マナーを守って利用すれば、快適な学習環境を手に入れることができますよ。
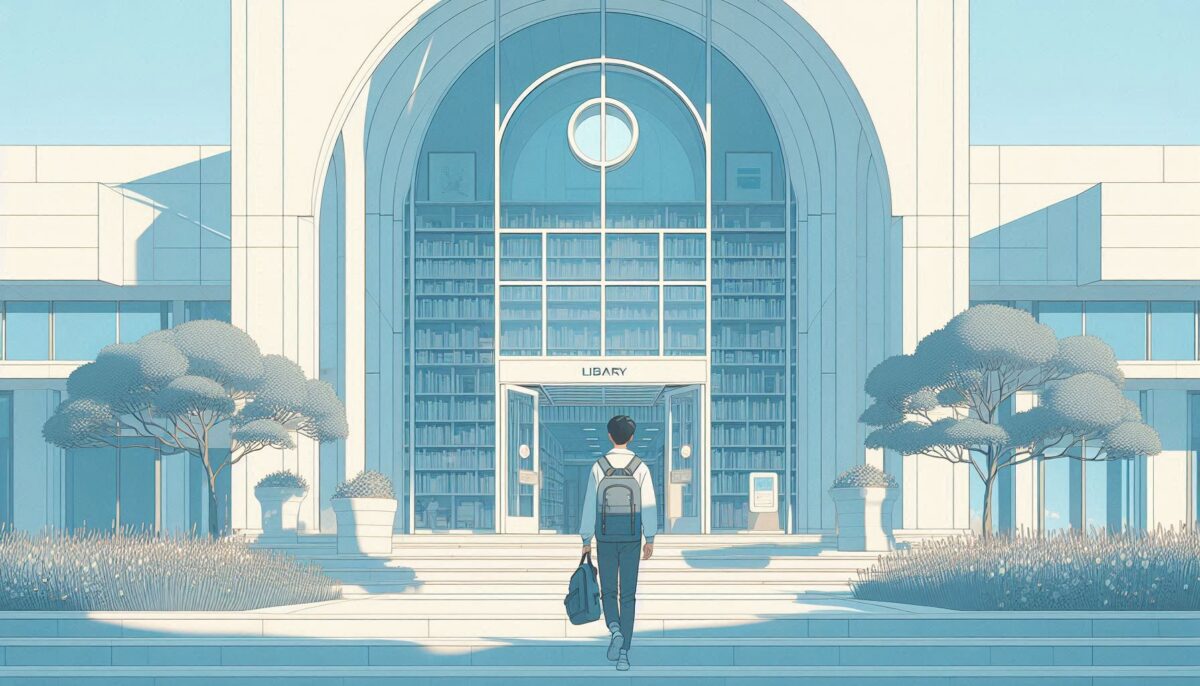

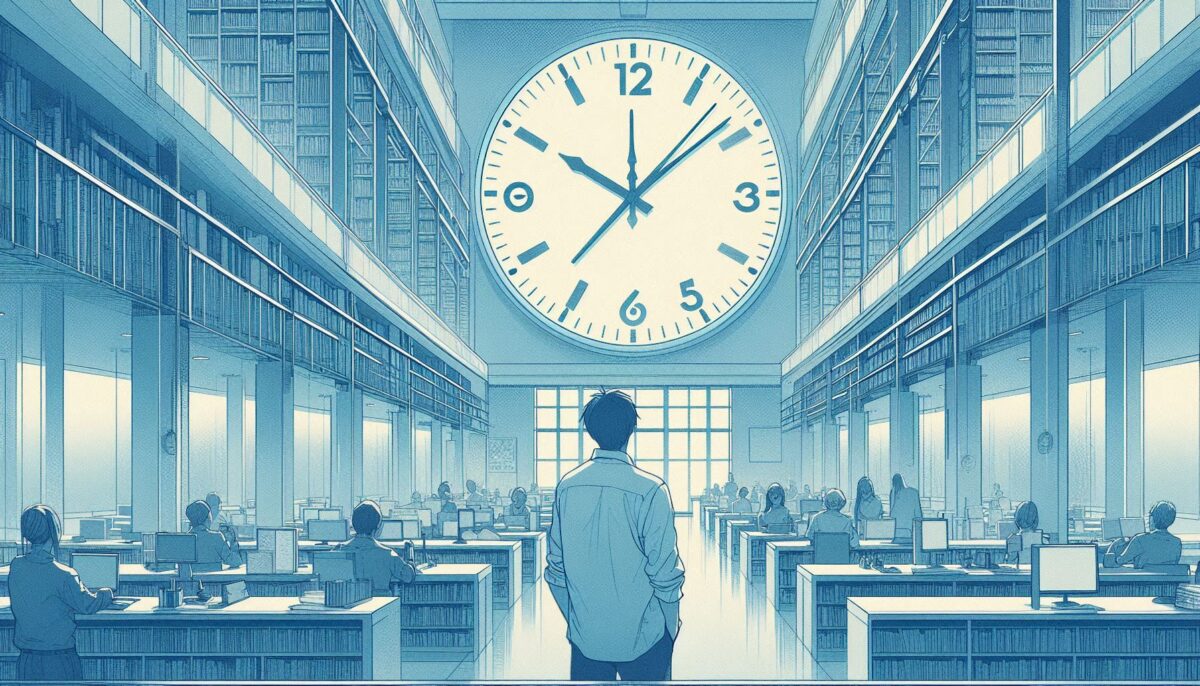
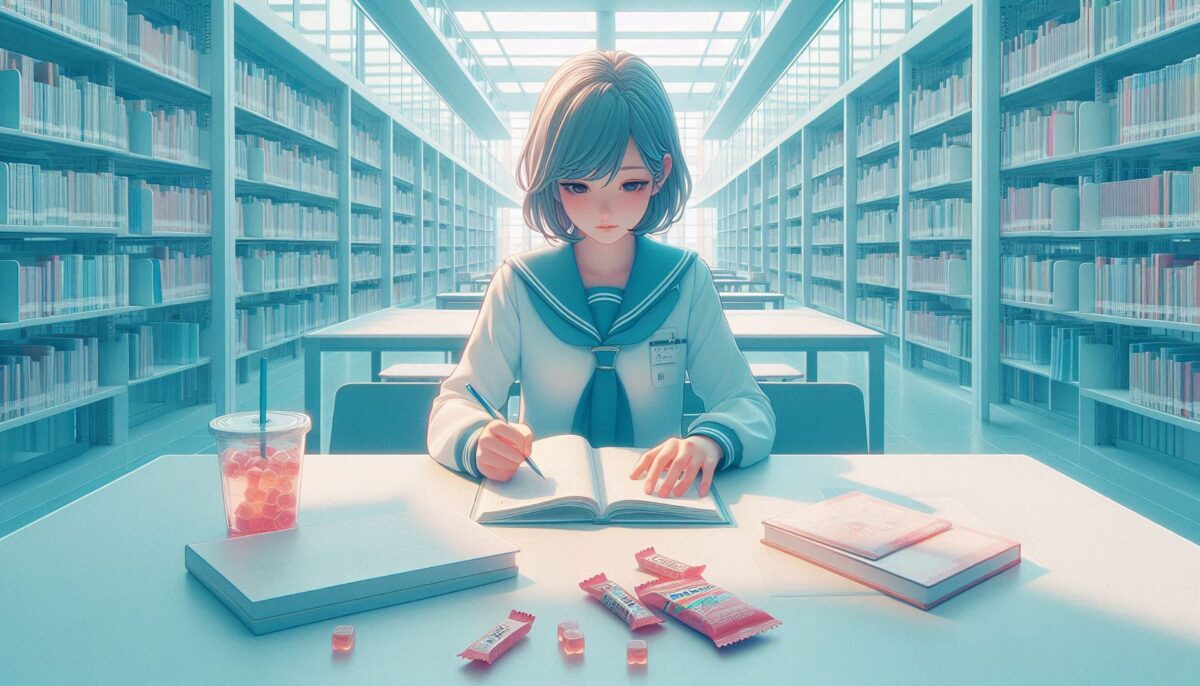
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://library-navi.com/people-from-outside-the-city-studying-at-the-library/trackback/