図書館に一日中いるとき、ご飯はどうしたらいいのか、正直迷いますよね。
私も学生時代に図書館にこもって勉強したときは「お昼ってどうするんだろう?」「お弁当持って行っていいのかな?」と不安に思ったのを覚えています。
まず最初に要点だけをまとめると……
- 図書館内での飲食は基本的に禁止されている
- 食事は館外か指定の飲食スペースで摂るのが原則
- 弁当や軽食を持ち込む場合は匂いや汁気のないものを選ぶ
- 長時間席を離れる場合は荷物をすべて持って行く必要がある
- 飲料は蓋つきのペットボトルや水筒のみ持ち込み可能な場合がほとんど
この記事では、図書館で一日中勉強する人のための実践的な食事のとり方や、守るべきマナー、そして多くの人が気になるQ&Aまで詳しく紹介していきますよ。
それでは、具体的な対策方法を見ていきましょう。
図書館に一日中いるとき、ご飯はどうする?
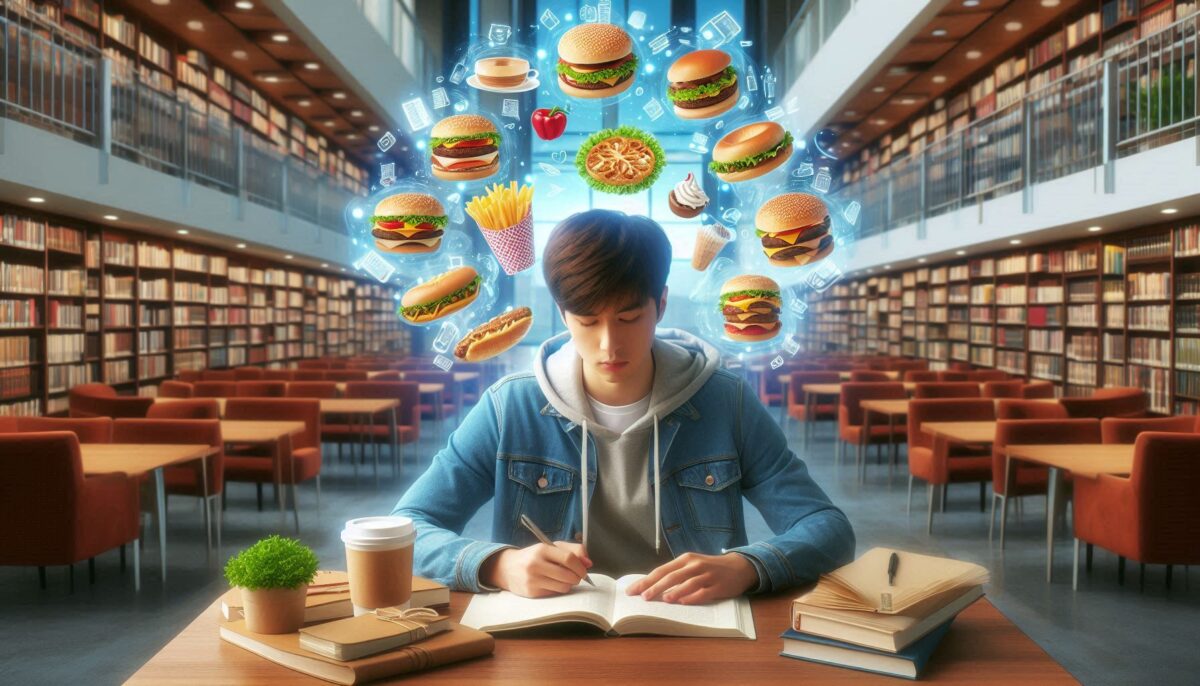
図書館で長時間勉強する場合、食事をどうするかは重要な問題です。
図書館は資料保全のため「飲食禁止」が基本原則となっており、一日中利用する場合は施設のルールを厳守する必要があります。
主な選択肢は以下の3つ。
- 弁当持参または買い食い(館外や指定エリアで食べる)
- 外食(図書館の建物外に出る)
- 軽食で済ます(指定エリアで食べる)
それぞれにメリットと注意点があるので、あなたの勉強スタイルや利用する図書館のルールに合わせて選ぶことが大切です。
次の項目からは、各選択肢の具体的な注意点を詳しく解説していきますね。
選択肢は3つ(弁当持参か買い食い・外食・軽食で済ます)
図書館で一日中過ごす際の食事方法には、大きく分けて3つのパターンがあります。
まず弁当持参または買い食いは、事前に用意した食事を館外や指定の飲食エリアで食べる方法です。
コストを抑えられるというメリットがありますが、食べる場所のルールをしっかり確認する必要があります。
次に外食は、図書館の建物を完全に出て近隣の飲食店などで食事をする方法。
好きなものを自由に食べられる反面、再入館の手続きや席の確保について事前に知っておくべきことがあります。
最後に軽食で済ます方法は、図書館内の指定エリアでおにぎりやサンドイッチなどの簡単な食事で済ませるやり方ですね。
時間のロスが少ないのが魅力ですが、許可される食品と禁止される食品をきちんと把握しておく必要があります。
どの方法を選ぶにしても、資料の汚損を防ぎ、他の利用者に迷惑をかけないという図書館の基本理念を守ることが最重要です。

弁当を持参したり買い食いする場合の注意点
お弁当を持って行きたいと考える人は多いと思います。
ただ、多くの図書館では館内での食事は全面的に禁止されているため、持ち込んだ弁当は指定された場所でしか食べることができません。
実際、M区の中央図書館やT大学附属図書館などでも、閲覧席での飲食は一切認められていないんです。
席を離れるときのルール
昼食のために席を離れる場合、これが意外と重要なポイントになります。
食事は一般的に30分から1時間以上かかるため、すべての荷物(特に貴重品)を携行し、完全に席を空けるのが正しいマナー。
「席取り行為」とみなされないよう注意が必要です。
■関連記事
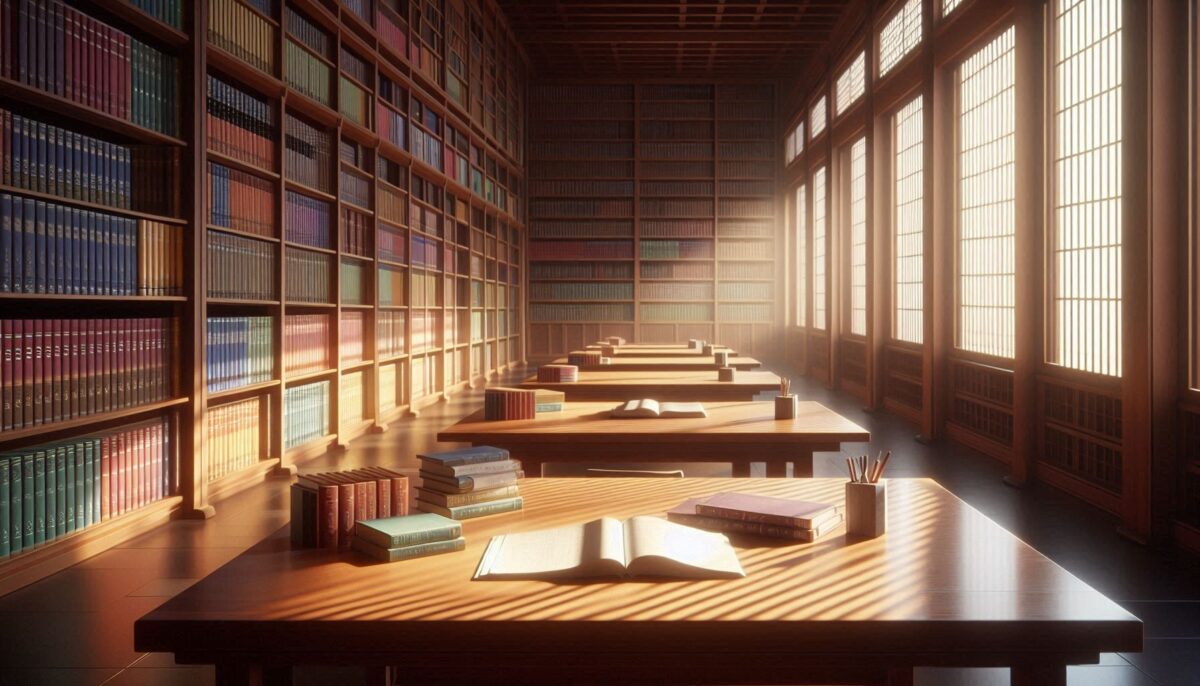
図書館に荷物を置いたまま外出(昼ご飯を食べる)してもOK?
図書館に荷物を置いたまま昼ごはんなどを目的に外出しても大丈夫?短時間の基準、貴重品管理のルール、他の利用者への配慮など、図書館利用のマナーを30年以上通う筆者が詳しく解説。盗難防止と席取り問題の正しい対処法がわかります。
図書館ナビゲーター食事ができる場所
多くの図書館では、以下のような場所が用意されています。
- 館外(建物の外)
- 入退館ゲートの外にあるリフレッシュエリア
- 指定された飲食コーナーやラウンジ
つまり、閲覧室や学習室では絶対に食べられないということ。
持ち込める飲食物の制限
休憩エリアであっても、何でも食べていいわけではありません。
| 禁止されるもの | 理由 |
|---|---|
| 汁物 (カップ麺、おでんなど) |
こぼす危険性 匂いが強い |
| 匂いの強いもの (カレー、揚げ物など) |
他の利用者への配慮 |
| 食器を使用するもの | 音が出る 洗い場がない |
やっぱり他の人のことを考えると、匂いの少ないシンプルなお弁当が無難ですね。
ゴミの処理
飲食に伴うゴミは、必ず指定のゴミ箱に廃棄するか、持ち帰る必要があります。
これは絶対に守らないといけないルール。
放置すると他の利用者の迷惑になりますし、図書館側も困ってしまいます。
外食する場合の注意点
完全に建物の外に出て、近隣の飲食店やコンビニで食事をする方法もあります。
なんていうか、これが一番自由度が高い方法ですね。
席の確保について
外食する場合の最大の懸念は「戻ってきたら席がなくなっているのでは?」という点でしょう。
長時間席を離れる場合は「席取り」とみなされるため、貴重品を含めすべての荷物を持って席を空けるのがルール遵守の基本です。
戻った際に席が埋まっている可能性はありますが、これが正しいマナーなんです。
とはいえ、混雑していない時間帯を狙ったり、平日の昼間を避けたりすることで、席を確保できる確率は上がります。
外食のメリット
外食の良いところは、図書館のルールを気にせず好きなものを食べられること。
- 匂いの強いラーメンやカレーもOK
- 温かい食事で気分転換できる
- 汁物も自由に食べられる
- しっかりした食事で午後の勉強に備えられる
特に試験前の追い込み期間など、栄養をしっかり摂りたいときには外食がおすすめです。
再入館の手続き
昼食の残りである紙コップのコーヒーは基本的に持ち込みはできません。
また、昼休み時間中は入館できない図書館もあるので、開館時間を事前にチェックしておくことが大切。
時間を計算に入れて行動しないと、思わぬところで時間をロスしてしまいます。

軽食で済ます場合の注意点
「がっつり食べなくても、軽く何か食べられればいい」という人には、軽食という選択肢があります。
ただし、閲覧席では軽食であっても一切の食事は禁止されているので注意が必要です。
許可される場所
軽食を食べられるのは、図書館が指定した以下のようなエリアのみ。
- リフレッシュコーナー
- 飲食ラウンジ
- 軽食スペース
- 入館ゲート付近の休憩エリア
これらのエリアがない図書館では、軽食であっても館内で食べることはできません。
許可される軽食の例
指定エリアで食べられる軽食は、基本的に以下のようなもの。
| 食品カテゴリー | 具体例 |
|---|---|
| おにぎり系 | おにぎり (シンプルな具材) |
| パン系 | サンドイッチ ロールパン 菓子パン |
| お菓子系 |
クッキー エネルギーバー |
| その他 |
ゼリー飲料 アメ |
共通しているのは、手でつまめるもので、匂いや汁気がないものという点ですね。
禁止される食品の例
逆に、指定エリアであっても禁止されることが多い食品がこちら。
- 汁物(カップ麺、スープ、味噌汁など)
- 匂いの強いもの(カレーパン、揚げ物、キムチなど)
- 食器を使用するもの(丼物、麺類など)
- 温める必要があるもの(冷凍食品など)
まぁ、考えてみれば当然ですよね。
図書館は静かな環境を保つ場所なので、匂いや音が出るものは避けるべきなんです。
飲料の持ち込みルール
飲み物については、比較的寛容な図書館が多いです。
密閉された蓋つき容器(ペットボトル、水筒など)に入っている飲料は、閲覧席でも許可されることが多いですが、紙パック、缶、紙コップなど密閉できない容器は指定エリア外への持ち込みが禁止です。
| 持ち込みOK | 持ち込みNG |
|---|---|
| ペットボトル (蓋つき) |
紙パック (ストロー付き) |
| 水筒 (密閉できるもの) |
缶 (開封後密閉不可) |
| タンブラー (蓋つき) |
紙コップ (カフェなど) |
つまるところ、「こぼれない容器」かどうかが判断基準になっているわけです。

図書館に一日中いるとき、ご飯は?に関するQ&A
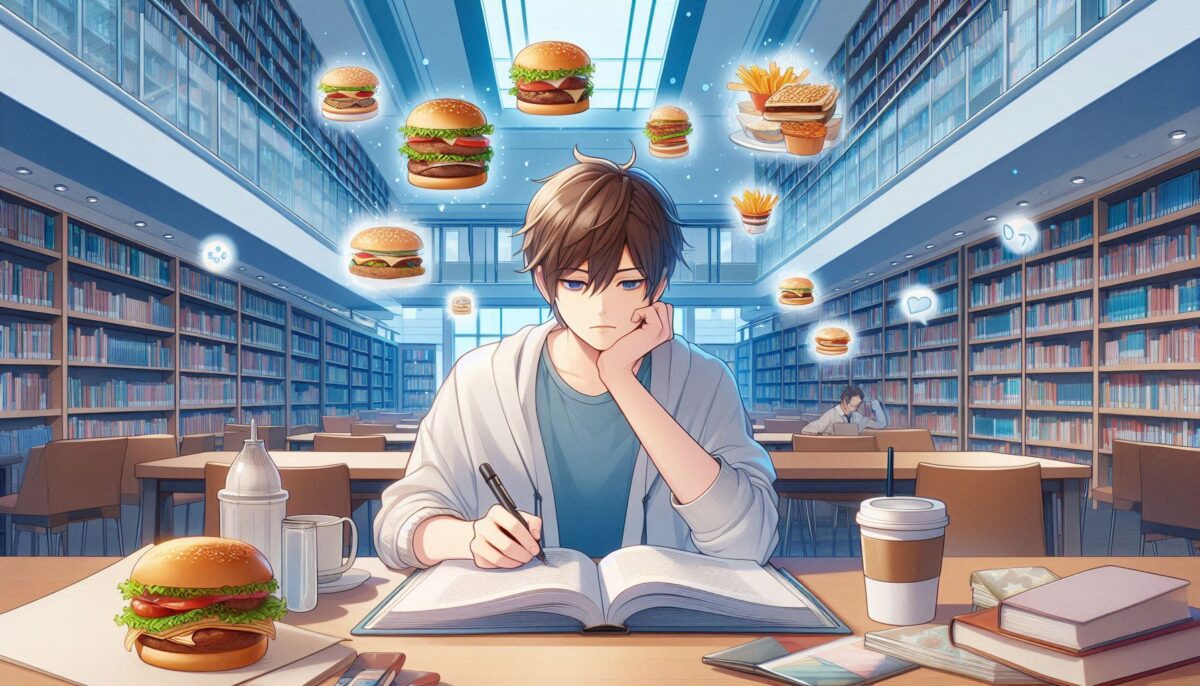
図書館で長時間勉強する際の食事について、よくある疑問をまとめました。
実際に多くの人が気になっているポイントを2つ取り上げて、詳しく解説していきます。
- 飲まず食わずで勉強している人は実際にどれくらいいるのか
- 他の人に迷惑をかけない食べ物の選び方
それでは、一つずつ見ていきましょう。
飲まず食わずで勉強する人も多い?
「図書館で一日中勉強する人って、みんな食事どうしてるんだろう?」と気になったことはありませんか?
実は、長時間静かに集中したいという理由で、飲食を控える利用者は一定数存在します。
特に試験前の追い込み期間や繁忙期には、そうした傾向が強くなりますね。
なぜ飲まず食わずで我慢するのか
その理由はいくつかあります。
- 席を離れると戻ってきたときに席がない可能性がある
- 食事のために荷物を全部持って移動するのが面倒
- 集中力を途切れさせたくない
- 図書館の飲食ルールがよく分からず不安
- 食後の眠気を避けたい
多くの図書館は飲食を禁止または指定エリアのみに限定しているため、飲まず食わずで我慢している利用者もかなりいるのが実情なんです。
勉強を頑張るためにもなにか食べるべき
ただ、これはあまりおすすめできません。
長時間の勉強には適度な栄養補給が必要ですし、水分を取らないと集中力も低下してしまいます。
さすがに丸一日何も食べないのは体に良くないですよね。
最低でも水分補給は欠かさず、可能であれば軽食を摂るようにしましょう。
賢い食事のタイミング
飲まず食わずを避けるための工夫として、以下のような方法があります。
- 開館直後や閉館前の空いている時間に食事を済ませる
- 混雑していない平日の昼間に外食する
- 指定エリアでおにぎりなど簡単なものを素早く食べる
- ブドウ糖タブレットなど手軽に摂取できるものを活用する
なにはともあれ、健康第一で勉強することが大切です。
においや咀嚼音がない食べ物といえば?
図書館の「軽食可」エリアで食べる場合、他の利用者への迷惑にならないよう「匂い」や「咀嚼音」に配慮することは非常に重要なマナーです。
特に静かな環境で勉強している人にとって、食べ物の音や匂いは集中力を削ぐ大きな要因になってしまいます。
匂いや汁気がない食べ物
まず、匂いが少なく汁気のない食べ物としては以下のようなものがあります。
| 食品カテゴリー | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| おにぎり | 塩むすび 梅干し 昆布 |
シンプルな具材を選ぶ |
| サンドイッチ | 卵サンド ツナサンド |
常温保存可能なものが無難 |
| パン | ロールパン クロワッサン |
匂いの強い具材は避ける |
ただし、これらはリフレッシュエリアなどの指定された場所でのみ許可されます。
閲覧席では絶対に食べられません。
無音で食べられるもの
咀嚼音が出ない、または出にくい食べ物も知っておくと便利です。
- アメ、キャンディー(噛む必要がないため無音)
- ラムネ(ブドウ糖でエネルギー補給にも最適)
- ハイカカオのチョコレート(集中力アップ効果も)
- ゼリー飲料(柔らかく音が出にくい)
とはいえ、これらも「食事」とみなされ禁止されている図書館が多いため、休憩スペースでの摂取に留めるべきですね。
避けるべき食べ物
逆に、絶対に避けるべき食べ物がこちら。
| 食品 | 避けるべき理由 |
|---|---|
| ポテトチップス | 咀嚼音が非常に大きい |
| せんべい | バリバリという音が響く |
| ガム | 咀嚼音が継続的に出る |
| リンゴ | シャリシャリという音が出る |
こういうものは図書館では控えるべきです。
勉強効率を考えた食べ物選び
匂いや音だけでなく、勉強効率も考えて食べ物を選ぶとさらに良いでしょう。
- ブドウ糖を含むもの(脳のエネルギー源になる)
- 血糖値が急激に上がらないもの(眠気を防ぐ)
- ビタミンB群を含むもの(集中力維持に役立つ)
- タンパク質を含むもの(腹持ちが良い)
例えば、ナッツ類やチーズ、ヨーグルトなどは栄養価も高く、音も匂いも控えめでおすすめです。
ただし、これらも指定された飲食エリアでのみ食べるようにしましょう。

図書館に一日中いるとき、ご飯は?のまとめ
図書館に一日中滞在する際の食事について、選択肢や注意点を詳しく見てきました。
最後にもう一度、重要なポイントを振り返っておきましょう。
- 図書館内での飲食は基本的に禁止されており、食事は館外か指定の飲食スペースで摂るのが原則
- 弁当や買い食いをする場合は、匂いや汁気のないものを選び、ゴミは必ず持ち帰るか指定のゴミ箱に捨てる
- 外食する場合は、長時間席を離れることになるため荷物をすべて持って行く必要がある
- 軽食で済ます場合は、指定エリアでのみ食べられ、おにぎりやサンドイッチなどシンプルなものが無難
- 飲料は蓋つきのペットボトルや水筒のみ閲覧席への持ち込みが可能
- 匂いや咀嚼音に配慮した食べ物を選ぶことが、他の利用者への重要なマナー
図書館で一日中いるときのご飯のとり方は、利用する図書館のルールによって変わってきます。
あなたが利用したい具体的な図書館の「飲食ルール」や「リフレッシュコーナーの場所」を公式サイトで確認し、そのルールに沿って行動することが、最も正確で安全な対処法です。
資料の汚損を防ぎ、他の利用者に迷惑をかけないという図書館の基本理念を守りながら、快適に勉強できる環境を作っていきましょう。
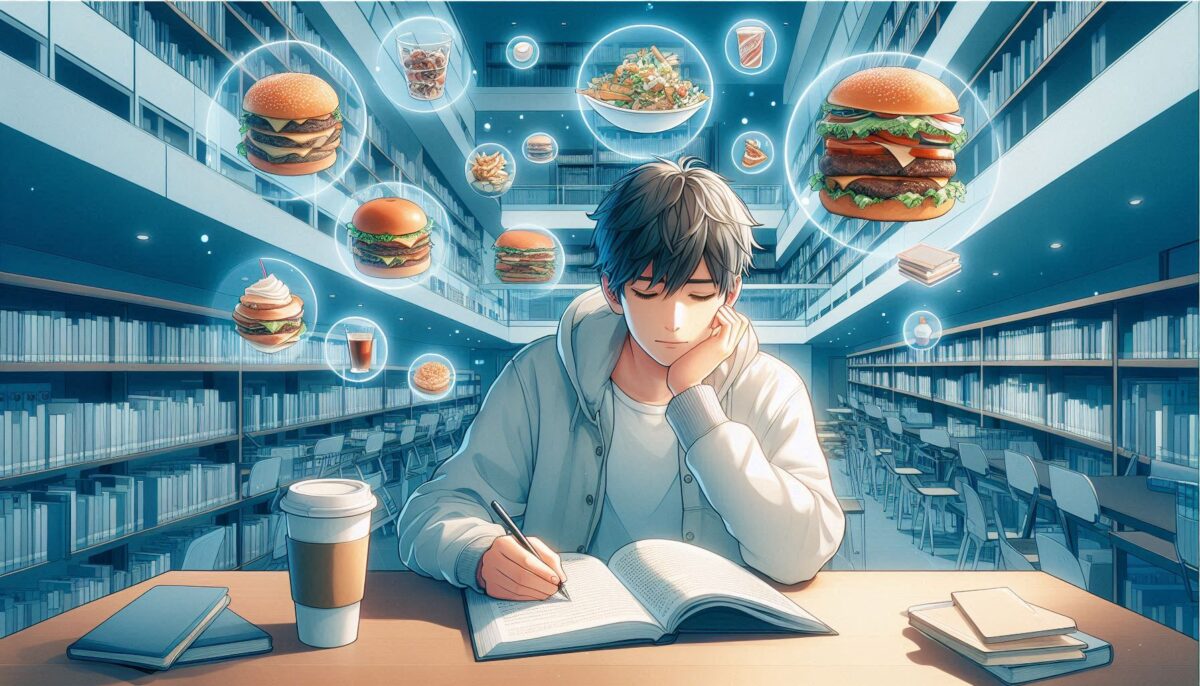
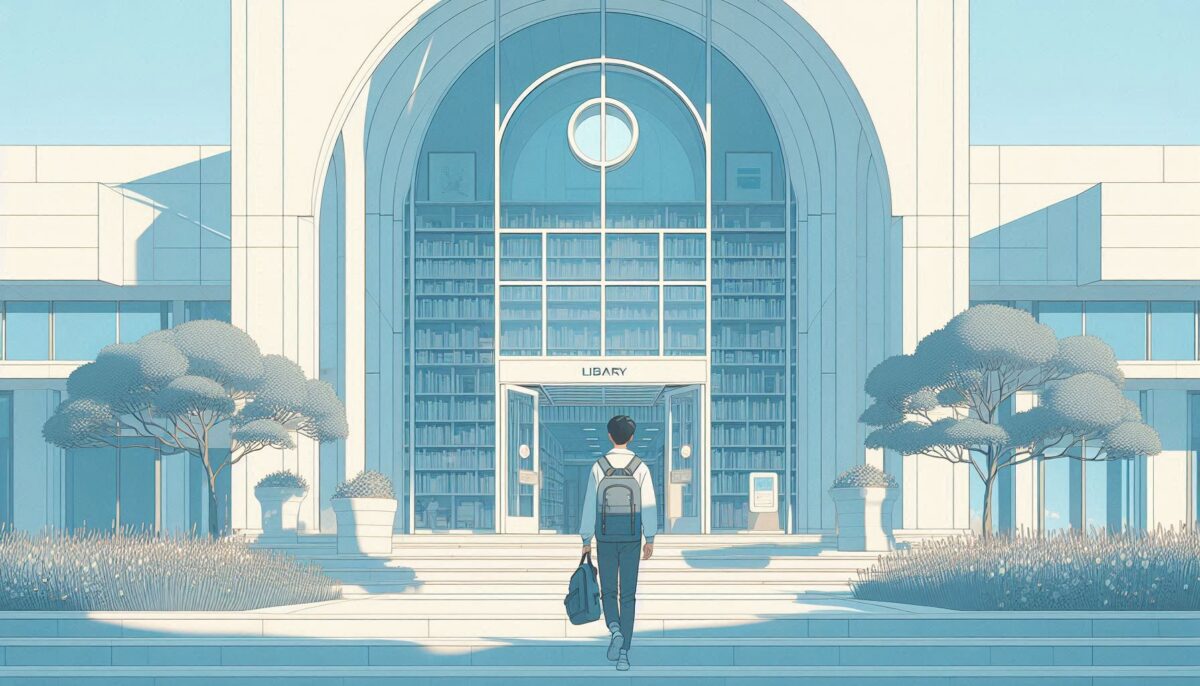

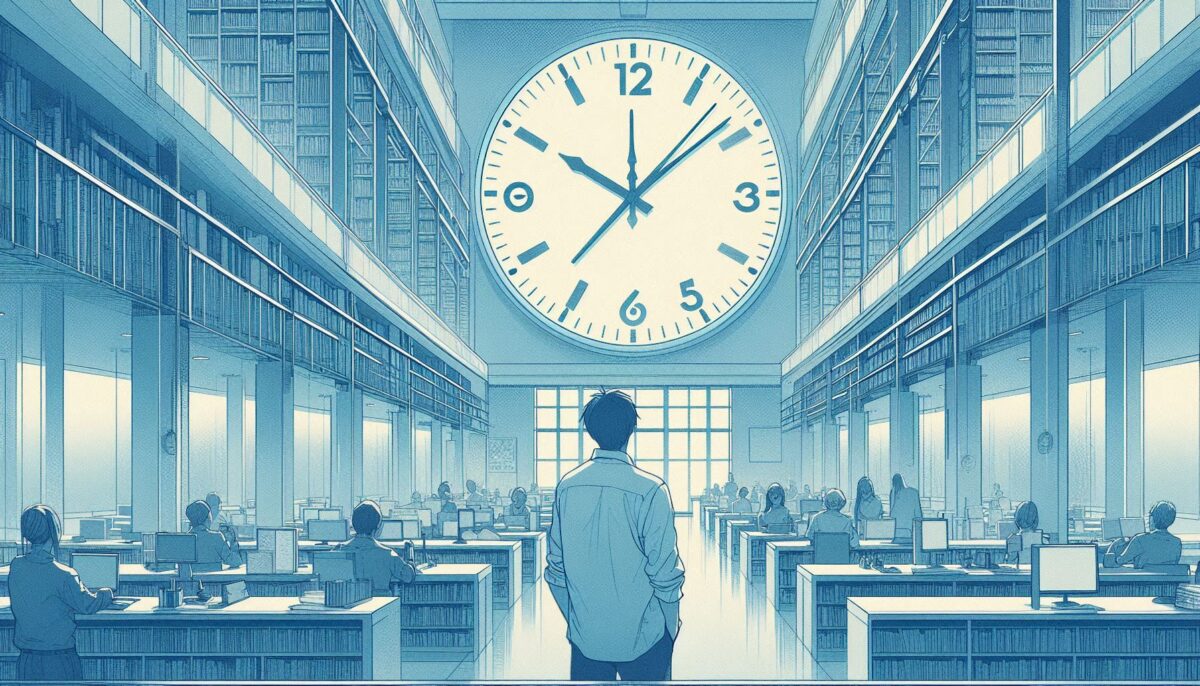
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://library-navi.com/meals-when-spending-the-whole-day-at-the-library/trackback/